『聖夜天』~四龍島Christmas 3~
- yz0824
- 2023年3月31日
- 読了時間: 5分
降誕祭だ。
本土居留区あたりでは賛美歌もとうに尽きたころ。
「あんたは、俺がそれを、ありがたがると思うのか。マクシミリアン」
「喜ばないと言うのなら、強いてでも喜ばせるまでだ。花路」
押しつけられたのは濃紺に銀砂子の飾り帯。
まるで暗闇に星を撒いて織り上げたようなそれを「何とはなしにこの男に似ている」と思いながら飛は見た。
マクシミリアンが冷ややかに迫る。
「白龍屋敷執事に加え、本土の王老人までをも煩わせてあつらえさせた品だ。謹んで受けるのが礼儀というものだろう、色街の頭」
「あいにく、山の手の流儀は知らない。俺が知るのは色街のそれだ。花路では、客が女に無理強いするのを無粋だとして退ける」
受け取れと命じられたが手はのばさなかった。
わざわざ呼び出し、特別あつらえだからもらい受けろと強いる。
もしも心惹かれる品であったとしても、唯々諾々とうなずくわけにはいかない。
思いどおりにはならないと、飛はマクシミリアンの美貌を仰いできっぱり拒んだ。
銀灰の瞳が性悪に笑む。
「わたしを嫖客になぞらえたな」
それではおまえは無理強いされた色街の娼妓か、と嗤うやいなや、相手がやにわに間合いを詰めにきた。
すかさず後退るところへ、もらい手のない帯をひらりと鞭のように振るわれる。
煌めく銀砂子に捕らわれた。
……しまった。
腰に巻きつく帯で、ぐ、と引き寄せられ、
「夜伽の侍女を帰しておいて、その後の主の機嫌をどう取るつもりだ。花路」
「女を下がらせたのはあんただ、マクシミリアン。色事を望むなら、いまからでも呼び戻せばいい」
「心得ているだろう、飛蘭。西里の『龍』は堪え性がない」
飛蘭、と。
ふいに実の名を耳もとで呼ばれて、つい抗い損ねた。
いまから悠長に女を呼び戻したのでは間に合わないぞと、せせら笑う相手に不意を突かれ、足もとをすくわれる。
ど、と倒れ込むのは寝台の上。 絹の褥に二人して沈み、薄い帳の波に呑み込まれた。 すぐさま跳ね起きるつもりが、すばやく目隠しをされた。
ざら、とまぶたに触るのは、たぶん銀砂子。 左の耳朶の翡翠に帯がこすれて、ちりりと痛みが走る。
「よせ」
「見苦しいぞ。してやられて無様にもがくのが色街の流儀とやらか」
痛烈な皮肉を吐かれて、仕方なし、といったん四肢の力を抜いた。
一市の『龍』が、街の護りを委ねる男を組み敷きながら、
「花路」
「おう」
「受け取らないか、帯を」
「……たとえ旨酒でも、飲みたくもないところに注がれれば苦いだけだ」
「西里産の糸を夜の色に染めさせ、本土紅海の銀糸を絡めて織らせたものだ。房飾りは王老人の見立て。薫き染めた香りは、好みでもない沈香。喜ばないか」
押しつける声音でマクシミリアンが強いてよこす。
この男は何を言うのだと訝しむ途中、はた、と思い至った。
「沈香は」
俺の好みだ、と。
つい口にしかけて、危ういところで飲み込んだ。
夜の色に銀糸……帯の向こうで、マクシミリアンがどういう顔をしているのかわからない。
得たり、と意地悪く嗤っているか。
それともまさか、真顔で口説くのか。
と、しなやかな指が、つ、と顎に触れ、領子に触れ、喉もとの紐子を焦らすように弄ぶのに気がついた。
「放せ! 『白龍』」
今度は躊躇うことなくはねつけた。
何のことはない。
色街の流儀を心得ているのは、自分ではなく、かえって相手のほうなのだ。
甘い文句で娼妓が客を蕩かすように、
客が好みの品で女の気を引くように、
迂闊にもお株を奪われたのだと、飛は舌打ちして、ふたたび四肢に力を込めた。
目もとから帯を引きはがし、ぴしり、とそれでマクシミリアンの胸を打つ。
「満天の星を引きずり下ろして帯に織らせたとしても、受け取るものか。もしも俺を喜ばせたいと願うなら、西里の平和、島の平穏をたゆまず織ることだ」
余計なことにうつつを抜かさず街の主としての務めを果たせ、と叱咤する。
体を起こすマクシミリアンが、ひやりと声音を尖らせた。
「そうして織らせた平穏とやらで、ついでにわたしを縛り上げるわけか」
「ああ、そうだ。あんたがたやすく縛られるというのなら」
冷えた双眸を、飛はまっすぐに見据えて立つ。
「それとは別に、花路の束ね役の腰を何かで飾りたいと酔狂な気を起こすなら……あんた自身が帯になることだ。四龍島西里の龍を結わえたなら、色街の袍には当然似合いのはず」
強気に口走って聞かせると、仰ぎ見る相手が秀麗なおもてにじわりと喜悦の色を滲ませた。
突き返された新調の帯をはらりと床に捨て、マクシミリアンが惜しげもなく踏みつける。
「なるほど……聖夜が聞いて呆れる淫猥な申し出だぞ、花路。神が慌てて耳をふさいだことだろう」
「否、ここは四龍島だ。『龍』のほかに神なぞない。あんたのほかに仰ぐべき相手がどこにある」
す、と差しのべられる腕に腰を抱かれた。
冷たい双眸と間近に見合い、
……夜に、銀糸。
この瞳で糸の色なぞ選ぶのかと呆れ、得も言われぬ心地にとらわれる。
と、ふいに、
「甘いことを考えているだろう、花路」
「あんたの思い過ごしだ、『白龍』」
胸の奥底までをやすやすと見通す銀灰の瞳を仰ぎながら、
……きっと花路の袍に似合ったはずだ。
美しい帯がさんざん踏みにじられるまえに、窓辺に寄った。
「遅くに邪魔をした。明日の晩、また」
ひら、とそこを越えると、庭木を足がかりに凍てつく夜のなかへ。
色街まで降りる道すがら、満天の星空をチラと見上げて飛は苦笑する。
煌めく天河が濃紺の中央をうねり流れている。
星々がせつなげに瞬いている。
まるで、聖なる龍に離れがたくまとわりつく花のようだ……。
[終了]

illustrated by 浅見 侑さま【禁複製転載】













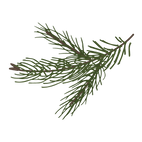
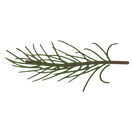

コメント