『去年の春 君を知りぬ』~kozo no haru kimi wo sirinu~
- yz0824
- 2023年3月31日
- 読了時間: 7分
四龍島西里、花路。
「聞いてくださいよ、頭。俺はもうどうしていいんだか、てんでわかりません!」
孫大兄が弱り切った様子で床に座り込んでいる。
羅漢のねぐらの古妓楼だ。
色街界隈の端である。
夜が明けてだいぶ経つというのに孫がいっこうに引き揚げようとしないので、渋面の羅漢が時おりあくびを噛み殺していた。
飛はついいましがた用事をすませて、ここへ来たばかり。
「いったいどうした、孫」
「よせ、飛。話を聞いてやると長くなるぞ」
事情を聞こうと声をかけたが、すかさず羅漢にとめられた。
「例の痴話喧嘩だ。どうにもならん」
孫は頭を抱えて”重症”の体である。
「悩んでいるのを放ってはおけない。先に休んでくれ、羅漢。孫、話を聞こう」
「さすがは頭、頼りになります!」
渋い顔で羅漢はのそりと寝台に潜り込み、孫がパッと顔を上げて喜んだ。
「実は、お嬢さんのことなんです。どうやらまたご機嫌を損ねちまったようで。いったい何が悪かったんだかわからねぇ……」
恋が悩みの種だという。
世話になっている商家の一人娘が、孫大兄の好いた相手である。
娘は火薬を扱う店里を女だてらに背負って立とうという勝ち気で、孫のほうは〃色恋ご法度〃の花路の兄貴分。
互いに想いは通じているものの、様々のいきさつがあって〃いい仲〃というところまではすすみかねているのだった。
飛もそのへんのところは承知している。
「こないだ、初めてお嬢さんと出会った場所で、珍しく二人っきりになったんです。そしたらお嬢さんが言うんですよ。
『あたしと初めて会ったときのこと、覚えてる?』って。
だから『そりゃあ、覚えてます』と答えたんです。
そしたら『あたしのこと、どう思った?』って訊くんです」
寝台の帳の奥で、羅漢が軽く咳き込むのが聞こえる。
いい加減なところで切り上げさせて、早く休めという合図に違いない。
孫はまるで高楼街あたりの猛者と取っ組み合うような顔色だ。
肩を怒らせ、顔を赤くして、拳をぎゅっと握り締めている。
なだめる口調で飛は訊いてやる。
「それで何と答えたんだ、孫」
「俺は真正直に言ったんです。『気に食わねぇ感じだと思いました』って」
寝台から羅漢の溜息が聞こえてきた。
孫がいっそう嘆き声を高くする。
「そしたらとたんにプイッとそっぽを向いたっきり、今日まで口を聞いてくれません。
『あたしに嘘を言ったってすぐわかる。嘘ついたら承知しないから』っていつも言うもんだから、隠さず本当のところを白状したってのに。
いったい何がどう気に障ったんだかわかりません」
俺はどうしたらいいんでしょう? と、花路の猛者がすっかりお手上げだ。
飛は苦笑して問いかけた。
「いまはどう思うんだ、彼女のことを」
「いま? いまじゃそのぉ、かわいいと思うんです。
強気でお転婆なのは相変わらずですけど、そこがまたいいんです。
ちゃんと娘らしくなって、たまに色っぽいなんて思うこともあって……うっかりドキッとしたりもするんです」
「だったら、そう伝えればいい」
「でもあれ以来、俺を見るとピュッと逃げるんです。すばしっこくて伝える暇なんぞありゃしません」
「手紙はどうだ?」
「頭は、俺が字を書くのを見たことがありますか?」
「何か好みの品を贈る手は」
「相手は商家のお嬢さんですよ? そんじょそこらの飾りなんかじゃ満足しねぇに決まってます。
まえも銀細工を贈ろうとしてうまくいかなかったことが……」
「だが想う相手なら、心を込めて贈ればきっと通じる。たとえ花一輪だとしても」
「頭はお嬢さんを知らねぇから言えるんです! そもそも女ってのは一筋縄じゃいかねぇ強者ですよっ」
孫がわめくところへ、バサリと帳をはね上げて羅漢があらわれ、ゴツンとげんこつを一発食らわした。
「いい加減にしろ、孫! 飛を休ませないか」
* * *
しょんぼり肩を落とした孫大兄が去ったあと。
羅漢のねぐらでいささか仮眠をとらせてもらい、昼には山の手の白龍屋敷に顔を出した。
青龍市酒造組合の使いが挨拶に訪れている。
かつては古株の老人ばかりが出張ってきていたが、近ごろは若いものにも他市への使いをまかせてみようということらしい。
名代と称して来た青年が、初めて接する西里主人をまえに目を瞠り、息を呑んでいた。
拱手したきり突っ立ったままの相手をまえに「くっく」とマクシミリアンが嗤い声を吐く。
「西に巣くう〃半龍〃よと、東里あたりではさぞかし噂にのぼるだろうに。
いざ目の当たりにすれば声をなくすほどに醜悪か、この姿は」
銀糸の髪。
銀灰の瞳。
島にあっては確かに異相であるが、しかし、四龍島西の街を統べる『白龍』は、彫りの深い顔貌といい、ひやりと冷気をまとう背高い姿といい、見るものをして「神龍もかくや」と感嘆せしめるほどに麗しい。
「なあ、花路。使者をよくも脅したなと憤って、東里がふたたび大挙してこの街を攻めてくれないものか」
「戯れ言は控えてくれ、『白龍』」
容貌華麗にして、性質苛烈。
いらぬ争いを好む主人をぴしゃりと諫め、飛は控えている屋敷執事に目配せをして、酒造組合の使いをいったん別室に引き取らせた。
ゆったりと長椅子に体を預けつつ、マクシミリアンが笑みのつづきをくちびるにのせる。
「珍奇な容姿も、時には使い勝手のいい秤になる。
西里の『龍』をまえに、あからさまに動顛するのは小心者の善人だろう。
片や平然と笑みを浮かべてくだくだしい挨拶を述べる輩があれば、腹に一物ある悪党に違いない」
善人の使者を丁重にもてなせ、と。
屋敷執事に向かって冷ややかに言いつけた。
いつもながらの痛烈な皮肉に呆れつつ、飛はマクシミリアンの双眸を仰ぐ。
「その姿が秤だと言うなら……初めてあんたに見えたときの俺の心を、どう量ったのかが知りたい」
銀灰の瞳が、す、とこちらを見下ろした。
「ほう。ずいぶんと懐かしげな言いようをするものだ」
言われたとおりだ。
この厄介な主と出会って、まだ二年と経ってはいない。
「あんたのせいで、だいぶ年をとらされた気分だ」
いろいろあった、と。
戯れのつもりで責めると、異相の『龍』が麗しい顔を凄艶に笑わせた。
戯れついでに飛は訊いてみる。
「あんたはどう思っただろう。初めて俺と出会ったときに」
マクシミリアンが低い美声で応じてよこす。
「気に入らん目をしていると思ったぞ」
「そうか」
「おまえはどうだ」
「似たようなものだ」
嘘だ。
いや、嘘ではない。
どちらだ、とみずからに問いつつ顧みた。
……恋に、似ている。
マクシミリアンに出会い、そう感じたのだった。
春だった。
まばゆく花が咲いていた。
なんと美しく、なんと危うげな男だろうと、
目が離せず、
息もつけず、
肌を粟立たせ、
舞い上がる心地で身を震わせた。
恋のようだと思いはしたが、あれほど誰かを夢中で乞うたことはいまだかつてない。
ならば恋をこれから知るかと訊かれて、うなずくことができない。
いま目のまえに仰ぐ男以外に、自分をこれほど奮い立たせるものがこの先あらわれるとは思えない……。
「どうした、花路」
何を考えている? と。
冷たいまなざしに問われて、ふと笑んだ。
厄介な恋路に思いを馳せていたのだと。
正直に白状したなら、果たして彼は何と応ずるだろうか。
花路に帰って孫に聞かせてやらなければいけない。
きっと、恋の相手は初めからおまえに夢中だったのだと。
出会った瞬間「好もしい」と惚れ込み、おまえが振り向くのを焦れながら待っていたに違いない。
〃気に食わない〃と〃恋しい〃がさして異ならない意味なのだと、手強い敵に悟らせないのは、おそらくこちらの手抜かりだ。
悠々と客を待たせて、異相の西里主人が窓辺にくつろいでいる。
冴え冴えと美しいその姿を見れば、あの日の昂ぶりがいともたやすく蘇る。
まるで、恋。
絶えず追いかけ、
焦がれているのだ。
これ以上の想いがあるというのなら、あんたが教えてくれ、『白龍』。
[再来]













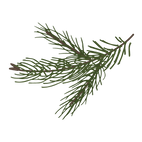
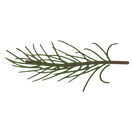

コメント