『翠玉揺々・・・花姫純情後話』~四龍島春2018版~
- yz0824
- 2023年3月31日
- 読了時間: 4分
白龍屋敷、南荘。
春の夜風が、ふわりと部屋のうちまで忍び入る。
「来たか、花路」
冷ややかな美声に招かれ、そこに足を踏み入れた。
身動きの邪魔にならぬ短衫。
背に打ち靡く漆黒の髪。
月明かりを受けてあらわとなる、しなやかな体躯。
居室の入り口を、す、とくぐる飛の姿は、まるで花影に休息を求める美しい夜の獣のようだ。
ふと見れば、上等の囲棋の盤が卓子に置かれている。
盤のそばに、翠色の小さな飾りがあると知って、いささか目を見開いた。
……かつて耳朶を彩っていた、契りの証。
龍を象る細工見事な、ひとつきりの翡翠の耳飾りだ。
「賭けるわけか、いいだろう」
囲棋の勝負に負けたなら、ふたたびその翠玉を耳朶に飾れと。
言わずもがなの相手の求めを応じて、飛は卓子のそばへと歩み寄った。
美貌の主が性悪な笑みを浮かべている。
四龍島西里主人、マクシミリアン。
銀糸の髪、銀灰の瞳。見るものの心を痺れ凍らせる異相。
冷ややかなまなざしはつねに余人を見下し、くちびるには嘲笑を湛える。
今宵の白龍市は、万事おさまるところにおさまり平穏至極。
滑稽なほど穏やかな鼓動をおのれの胸に聞きつつ、飛は棋子を手に取った。
「先手を譲ってもらおう。厄介な相手に付け入る隙を与えないように」
「北里に寄り道するあいだに忘れたか。先に攻めようが、あとに攻めようが同じことだ」
無駄な足掻きはよすことだと、勝負の行く末を透かし見るかのような文句をよこされた。
洋灯の揺らめく明かりのなかで、マクシミリアンの容貌はことさら冴え冴えと美しい。
まるで中天に輝く月が降りてきたような……と。
数瞬、盤の目を読むことを忘れて飛は魅入られる。
気を取り直して初手の棋子を、ぱち、と置く。
「七線、三目」
「定石か。らしくもない」
「あんたの打ち方は酔狂が過ぎる」
「北東角」
「……悪手かと思えばあとから効いてくる。いかにも西里の『龍』らしい」
「これしきで音を上げるか、花路」
「馬鹿な」
即座に応じつつ、それでも棋子を迷わせた。
「東点に、三棋」
攻めつつ、しまった、と舌打ちする。
思案が鈍るのは遠く聞こえる花炮のせい。
厄介事の一つもない夜に、つい気が緩むせいなのだと、いらぬ負け惜しみを自らに聞かせながら、もう数手。
「二線……」
盤の上に指を彷徨わせたところで、すでにあとがないと気がついた。
花の香りを含む夜気にやわやわと耳朶を撫でられる。
耳に聴く花炮の余韻。
爆竹の響き。
西里の夜天を賑わす音に酔いながら、負けを認める言葉がなぜか舌に甘いと感ずる。
「参った」
ぴしり、と。 マクシミリアンが、とどめの一手を鋭く差した。
「口ほどにもない」
「ああ、調子がくるった」
「ほう。どうしたわけで」
「強いて言えば、耳にうるさい花炮のせい」
……そして、あんたの。
勝負を落とすのは今宵かぎりだと言い添えると、銀灰の瞳に嗤われた。
〃立て〃と。
無言の指図をよこされ、引き寄せられるように椅子から腰を上げる。
長くしなやかなマクシミリアンの手指が、翡翠の飾りを、つ、と取り上げる。
「『白龍』。最初のときのような無理強いは、ごめんだ」
いつぞやのように不意打ちで痛みをよこすのはやめてくれと、せめてもの注文をつけるが、相手は笑んだまま何とも返事をよこさない。
邪魔になる髪をおのれでかきやりつつ、
「待ってくれ。領子を」
血で汚してはいけないと襟をくつろげるあいだに、マクシミリアンがくびすじに触れにきた。
暖かな春の宵だというのに、ぞく、と肌が粟立つ。
不快なような、
甘美なような。
まるで酩酊に引きずり込まれる心地だと戸惑ううちに、尖った針先を耳朶にあてがわれた。
いまか、と覚悟をして待ち構えると耳もとに、
「好みを聞かせると言っていたな、花路」
「何」
「忘れたか。囲棋のあとには色恋の話をと、言っていた」
そんな約束をしただろうと、マクシミリアンの嗤い声。
そういえば、そういう話をしたのだった。
〃好みを聞かせろ〃と、耳朶に針を突きつけられたまま求められ、何もこんなときに、と横目で相手を睨み、
「少なくとも、性悪でない相手」
「なるほど。いまその答えを吐くのが得策かどうか、よく考えてから舌を使うことだ」
「気紛れで性悪な龍が好みだと応えて聞かせたなら、その針先は余所へ向くわけか」
「この期に及んで憎まれ口を聞かせるのは、酷い仕打ちを好む証だろう」
「焦らすのもたいがいに、マクシミリ……」
瞬間、そこが灼けると息を呑んだ。
「つ、ぅ」
ぽたり、と首筋のどこかに血が滴り落ちる。
熱した耳朶に、ぐい、と翠色の証が刺し込まれた。
痛みの在りかをくすぐるように、冴えた美声がひとこと、
「艶だぞ、花路」
仰ぎ見る双眸が喜色を浮かべている。
そうだ。
この相手をまえにしたなら好手も悪手もありはしない。
たちまち手の内を見透かされ、いつの間にやら勝ちをさらわれる。
花炮を聞き、危うい鼓動が耳朶を苛むのを聞きつつ、苦笑する。
冷ややかなまなざしを受けとめ、甘やかな痛みを味わいながら、
「好棋」
あんたの勝ちだ、マクシミリアン。
ただし、今夜だけ。
[春終]













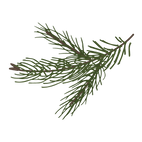
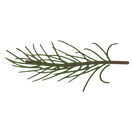

コメント