『夏暇』~四龍島ナツヤスミ~
- yz0824
- 2023年3月31日
- 読了時間: 8分
四龍島、西里。 暦の上ではそろそろ夏も過ぎようという時節であるが、昼間の暑気がいまだ冷めやらず、まるで家々の屋根が見えない炎を噴き上げて夜空を焼くようだ。
山の手の白龍屋敷である。
「街の主に夏暇(なつやすみ)というものはないか、執事どの」
執務室の窓辺に、す、と立ち寄って、マクシミリアンが冷ややかな声音を吐いた。
生ぬるい夜風に吹かれ、銀糸の髪が揺れている。
薄物とはいえ長袖の袍の領子をくつろげもせずで、白い額に汗ひとつ浮かせていない。
まったく美しいその容姿に、団扇で申し訳程度の涼を送る係の侍女が、先ほどから幾度も感嘆の溜息をこぼしていた。
こちらはこちらでお仕着せの袍をきっちり着込んで淡々と事務をこなす執事が、性質苛烈な主人の愚痴をさらりと聞き流す。
「夜になっても涼しさが訪れないのは、ほんの数日のことかと思われます。『白龍』」
このところの夏日のように容赦ない万里の返答に、マクシミリアンが、に、とくちびるの片端を吊り上げる。
「龍とはそもそも水に縁ある生き物だ。干上がっては使いものにならないだろう」
「おっしゃるとおりです」
「厄介な主は生かさず殺さず、時に手綱をゆるめつつ扱うものだ。白龍屋敷の使用人どもさえ、交替で暇をとっている」
「おっしゃるとおりです」
万里は手もとの書類を繰りながら、あいまに侍女に湯冷ましを運ぶよう言いつける。
「さて、船主組合の次回の会合についてですが……」
どうやら主に休暇を与えるつもりはさらさらないらしい。
* * *
色街花路には、当然のこととて、夏暇なぞはない。
「暑い夜こそ、あっつあつの包子だ! 今夜は蝦入りだぜ。お客さん、どうだい?」
「冷やした瓜だよ。馴染みの女に会うまえに口を甘ぁくしていきなよ」
花燈籠が揺れる道筋に、少年たちが出て客を迎えている。
小机を出したり籠を担いだりして食いものを売りながら、界隈の治安にくるくると目を配る。
道の角や流行りの妓楼前、要所要所には兄貴分たちが詰めていて、酔客が喧嘩でもはじめようものならあっという間に駆けつけ、首尾よく騒ぎを収めるのだ。
「飛、おまえ、一日二日休んでいたらどうなんだ」
界隈端の古妓楼。
右腕と頼む仲間に言われて、飛はつい苦笑した。
手にした茶碗を床に置き、漆黒の髪をかき上げつつ、ちら、と羅漢大兄を斜めに見る。
薄暗闇のなか、紅でもつけたなら界隈で一二を争う美姫だと評判にもなりそうな、端正な顔立ちである。
流し目を送られた格好の羅漢が渋面を作って、ごほ、と少々茶にむせた。
身に纏うのは色街の男ども百余名を束ねる印の、刺繍入りの黒い袍。
敵を向こうにまわして立ち会えば、蹴り、拳を容赦なく繰り出し、自分よりよほど体格のいいごろつきを難なく倒してみせる。
見た目を裏切る猛者ぶりに、仲間が心酔しきって従っている。
喧嘩の腕とは裏腹の外見に正直惹かれてと、おおっぴらに鼻の下をのばすものもないではない。
「本当に熱はないのか?」
「ああ、大丈夫だ」
「あの葉林が食欲がないと言いだしたのが十日ばかりまえだ。次に孫のやつが三日も熱で寝込んだあげく『節々が痛くて死にそうなんです』と、どさくさ紛れにおまえにしがみついた。
昨夜おまえが俺のところで『少し横になりたい』と言ったときには、さては孫のやつからうつされたなと思ったんだが」
夏風邪をひいたのではないかと心配をよこされ、ぐ、と腹に力を溜める飛である。
「この暑さで苛立つ客もある。花路は夜を昼にして賑わう界隈だ。客の気晴らしどきは、こちらにとっての働きどきだろう」
朝になってから、いくらでも休める。心配をかけてすまない、と微笑んでみせた。
つとめて勢いよく袍の裾を払って立ち上がり、
「見まわりに出るとしよう」
「おう、俺もすぐにあとから行くぞ。孫のやつに会ったら、派手にくしゃみを引っかけてやれ。他人にうつすと早く治るそうだからな」
もらった風邪に利子をつけて返してやれと言う羅漢をあとに残して、古妓楼二階から石畳の道へと降りた。
夜風が生暖かい。
寒気を覚える体にとってはかえって心地いい。
賑わう道筋のほうへ視線をやると、燈籠の明かりがぼんやり滲んで見えた。
目を凝らすと軽い目眩に悩まされる。
……いざというとき、役に立たないでは仕方がない。
拳を握り、石畳を踏みしめてみて、どうやら四肢に力が入らないようだと顔をしかめた。
梅雪楼まえにはすっかり熱が下がって元気になった孫大兄が陣取っているし、あとから降りてくる羅漢は、年少の連中を引き連れながら界隈にくまなく目を配って歩んでくれるはず。
「裏手を、行くか」
まんがいち事が起きたときに仲間の足手まといになってはいけない。
自分は人の少ない暗がりを見まわろうと決めて、山の手への上がり道へと足を向ける。
地面の凹凸がやけに気になるのは、石畳の歪みのせいではなく、熱で体の平衡が取れないためだろう。
「参った」
世話になっている商家に迷惑をかけるわけにはいかないからと、羅漢のねぐらに転がり込んでいた孫の苦しみようを思い出して、肩をすくめる。
医生が起きていたら、帰るまえに薬を処方してもらおう。
ことによると明日は龍江街でおとなしくしていたほうがいいかも知れない。
玲泉に言って、なるべく顔を合わせないようにしてもらわなければ、と……
考えながらふと目を上げたところで、はた、と身構えた。
灯りが一つ、ゆらゆらと見えていた。
山の手につづく石段をこちらに向かって降りてくる。
足音が一つ、いや、二つだろうか?
……しまった。目が利かない。
ふだんであれば少々の隔たりがあっても、灯りを掲げる相手の姿、気配が見てとれるはずなのに。
舌打ちしつつ足を踏み出す。
「誰だ!」
誰何の声を発すると、灯りが弾かれたように飛び上がる。
どうやら二人連れであったらしい。
聞き慣れた嗤い声が降ってきた。
「殊勝にも出迎えをよこしたか。それとも運命とやらに導かれ、はからずも行き会わせたか」
花路、と。
呼びかけてよこす相手は、マクシミリアンだ。
ほ、と力を解いていいものかどうか飛はつかの間、迷った。
「『白龍』」
目眩を堪えつつ応じて聞かせる。
どうやら屋敷の小者に無理やり夜道の供をさせたらしい。
角灯を手にちらちらと山の手を気にかける小者の挙動から察するに、万里には無断に違いない。
マクシミリアンがさっそく用なしだとばかりに案内役を追い立てる。
「帰りは色街の猛者が送り届けてくれる。ごろつきどもの頭は別して夜目が利くそうだ。灯りも心配も無用に違いない」
小者があたふたと石段を駆けて去り、夏闇のなかに二人きり。
「加虐趣味のある屋敷執事から逃れてきたぞ。夏暇どころか、ろくに午睡さえ許されない。『龍』とはいつからこうも虐げられた立場になった」
その名を負わせた責任を取れよと、迫られて飛は苦笑する。
「そもそも一市の主人とは忙しくて当たり前だ。誰より重い荷を負い、寸暇を惜しんで人々のために勤しんでこそ、みな納得して従う」
「ほう、案外なことを聞くものだ。重い荷を他人にばかり負わせ、持て余すほどの暇を得るのが『龍』の仕事と思っていたが」
「あんたらしい思い違いだ、マクシミリアン」
それは間違いだと、笑い声をこぼした拍子にぐらりと体が傾いた。
……困ったぞ。
羅漢の言うとおり、おとなしく古妓楼二階で休ませてもらうか、早々に龍江街へ戻るべきだったと後悔する。
夜のなかでさだかには見えない銀灰の双眸がほくそ笑んだ気がする。
「花路、酔っているか」
「いや。酒は、飲んでいない」
「では暑気に負けたか」
「いや、そうではない」
弱みを見せてはならないとおのれを叱咤して、は、と気づけば、相手が間近に寄っていた。
思わず後退ったとたん、不覚にも石段を踏みはずした。
……あ。
助けを求めてのばしかけた手をとっさに止めた。
その腕にすがれば土に膝をつかずにすむ。
でなければ今夜は情けなく醜態をさらすことになる。
熱で鈍った体が言うことを聞かない。
手を借りて嗤われるのと、石段を落ちて嗤われるのと、果たしてどちらがマシか。
もしも……しがみついて「辛いのだ」と訴えたなら、この男はどういう顔をするだろう。
一度くらいそれを拝んでやりたい気がすると、おかしな迷いが起きるのはやはり病のせいに違いない。
この際ついでに、身のうちに巣くう悪い熱をなすりつけてやるのはどう。
休みがないのが不満なら、花路の頭に夏風邪をよこされたと言い訳すればいい。白龍屋敷執事もさすがに病床の『龍』には目こぼしをくれるはず。
どさ、と倒れる瞬間の痛みを待ったが、寸前でふわりと体が浮いた。
心地よさと危うさに同時に抱かれ、呆れつつ、ただで立ち直らせてはもらえまいと覚悟をした。
うるむ視界のなか、西里主人の美貌だけが冴え冴えとやけにはっきり見える。
ひやりと皮肉をよこされる。
「いいざまだぞ、花路」
「……意外だ。あんたがすすんで荷を手にすることがあるとは思わなかった」
そうだ。
夏暇とやらを、あんたにやろう。マクシミリアン。
手を貸したことへの礼はそれきりだと聞かせて、さて、性悪な主がうなずくかどうか……。
[夏終]













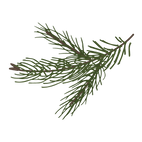
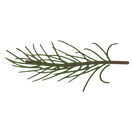

コメント