『春宵恋々・・・四龍島間奏曲』
- yz0824
- 2023年3月31日
- 読了時間: 5分
色街、花路。
孫大兄の鋭いまなざしがジッと石段を見据えている。
……今日こそしっかり頭をお守りしなけりゃあ。
羅漢大兄、葉林大兄についで三人目の大兄に立てられ、すでにそれなりの時が経つ。
そのひとが不在のあいだ、精一杯の努力をした。
過去の失敗を悔い、失くした信頼を取り戻して、再会ののち「よくやってくれた、孫」と認めてもらうためだった。
色恋御法度の花路にあって、恋しい女がないわけではない。
幼いころから世話になっている商家の一人娘とは〃恋仲未満〃のむず痒い間柄となっている。
それでも頭への想いは変わらない。
忠誠といおうか、ほとんど恋情といおうか、とにかく一途に彼を慕っている。
「孫兄貴。それで、俺たちはどうすりゃいいんです?」
「指図をください。いざとなったら殴りますか? それとも蹴りますか?」
引き連れた弟分二人が背後から逸る声をよこすのへ、
「いざとなりゃあ蹴っても殴ってもかまわねぇ。とにかく頭に指一本触れさせちゃならねぇ」
噛みつくように孫は言いつける。
「何しろ相手は本土育ちの海千山千だ。いままでだってやりたい放題、頭をいいようにしてきてる。隙を突いちゃあ、だ、だ、抱き寄せたり触ったり。嫌らしくて、助平で、とんでもねぇ卑劣漢だ。これ以上『白龍』のやつに、頭を好きにさせやしねぇ。そんなんじゃあ、花路百余名の名折れだ!」
そうだろう、と握る拳を震わせる。
「そりゃあ、冬からこっち俺も反省したし、一時は『白龍』を賢いおかただと見直しもした。けど、やっぱし頭の操のこととなると譲れねぇ。〃龍は花を負い、花は龍を負う〃っていうが、頭を負ぶったり負ぶわれたりしていいのは俺たち花路だけだ。そうは思わねぇか、なあ!」
潜む場所は界隈の隅。
白龍屋敷への近道となる石段そばの茂みである。
昼過ぎ、羅漢と飛が話すところにちょうど孫は居合わせた。
『おい、飛。夕方「白龍」がお忍びで立ち寄るそうだ。梅雪楼へどうぞと使いに伝えたが〃傷の大兄のねぐらあたりで構わない〃という返事だ。どうする?』
朽ちかけた床も階段も、いつ踏み抜かれてもおかしくない古妓楼を訪れられてはと、羅漢がいかにもな迷惑顔だった。
涼やかな笑みを浮かべて飛が言った。
『石段あたりで俺が出迎えよう。そのまま首尾よく梅雪楼に案内をする』
『ああ、頼むぞ。何人か引き連れていくか。孫のところの子分どもでもつけさせるか』
『いや、一人で迎えよう。そのほうが都合よく運ぶに違いない』
相手はこちらが一人のほうが機嫌がいいに違いない、と。
凜々しい笑み声が言うのを聞いて、無性に胸が灼けたのだった。
……ちきしょう、『白龍』め。
頭におかしなことをしやがったら、とんで出ていって「我らが頭への不埒な真似を、いい加減にお控えください」と断固文句をつけてやる。
やわやわと夜風の優しい、春の宵である。
しばらく茂みに隠れて待つと、古妓楼のほうから足音が聞こえてきた。
「来た! ありゃあ絶対に頭ですよ、孫兄貴」
迷いなく、すたすたと歩む靴音だ。
軽やかで、強く、きりと引き締まった足運び。
あたりはもう薄闇となっている。
ぽつぽつと灯りのともる時刻である。
角を曲がって飛があらわれた。
漆黒の袍に翡翠色の帯。
大事な客を迎えて界隈一の妓楼に案内するのにふさわしい装いだ。
『白龍』のために着替えたのだと思うと、孫は余計に気が気でない。
石段の下まで来て、飛はぴたりと立ちどまる。
腕組みになって静かにそこにたたずむ。
ちょうど頭上に花が咲いている。
夕暮れの景色のなかに仄白く、まるで待ち合わせの印の灯りをともしたかのようにほころんでいる。
そよそよと石段のほうから風が吹き寄せ、花枝が揺れる。
飛がまなざしを、す、とめぐらせた。
……頭?
仇を狙うように鋭い視線を向けていた孫だが、そうして見やるひとの様子に、はたと胸を衝かれた。
風の寄せてきた石段の上へと、まなざしを上げている。
薄闇のなかだというのに、まぶしげに目をほそめている。
しばらくすると「ふ」と笑みをこぼし、もとのとおりに向き直る。
無造作に髪をかきやり、その手を何とはなしに左の耳朶へと持っていく。
……待っているんだ『白龍』を。
気づいたとたん、キュウと甘い痛みに心の臓をつかまれた。
知っている。
自分にも想う相手がある。
慕わしいひとを焦れつつ待つ気持ちはよくわかる。
素直に「会いたかった」となかなか言えない。
足踏みを堪え、ウロウロ歩きまわりたいのを必死で我慢する。
こちらから出向いていけばいいのに「そんなことしたら負けだ」と意地を張って立ちどまる。
しきりに胸が鳴るのに知らんぷり。
でも実は、舞い上がるくらいに幸せだ。
「頭……」
じわ、と何かが込み上げ、思わず茂みから腰を浮かせるところで、そのひとが腕組みを解くのが見えた。
人の気配が降りてくる。
見ると、花路の頭のまなざしがきりりと冴えている。
先ほどまでの甘い目色とは異なる、凜として挑むような瞳の美しさだ。
うしろから「いまだ」と弟分たちが急かしてよこした。
「行きましょう、孫兄貴」
「早いとこ『白龍』をやっつけねぇと」
孫は、ぐ、と握る拳を振り上げ、軽くポカ、ポカと弟分たちにゲンコツをくれた。
「痛てぇっ」
「何するんですか、大兄」
最後に自分のあたまを、ゴツ、と強く打ち、
「引き上げるぞ。早くしろ。戻って梅雪楼まえに整列だ。頭が『白龍』をご案内するのを、みなでそろって出迎えるんだ」
……かなわねぇ。頭にあんな顔をさせる男を、とっちめられるわけがねぇ。
目を白黒させつつ弟分たちがあとからついてくる。
「孫兄貴、焼きがまわったみてぇだな」
「仕方がねぇよ。春だしな」
やわらかな夜風のせいで、猛者の調子もいささかくるうのだ。
仄白く咲く灯火の下では、つつがなく龍と花とが出会っている。
「薄暗がりで待ち伏せとは、いかにも賊どもの束ね役らしい。さては焦がれて彷徨い出てきたか、花路」
「不意の訪れでしばしば色街を騒がせてもらっては困るのだ、『白龍』」
[夜来]













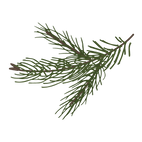
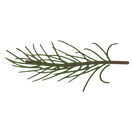

コメント