『龍は繙く』~Dragon's Day~
- yz0824
- 2023年3月31日
- 読了時間: 4分
四龍島、西里。白龍市。
山の手の白龍屋敷に大声が響いている。
「おおいっ、マクシム! マクシミリアン! 本を知らないか?」
クレイ・ハーパーが愛読書を探しているのだった。
回廊の角まで来てちょうど屋敷執事の万里に出会い、訊いてみる。
「ああ、万里。俺の本をどこかで見なかったかい?」
ぴたりと足をとめる万里が、落ち着き払った調子で返事をする。
「本といいますと、本土から送られてきた洋書でしょうか。それとも白龍屋敷の書庫からお貸ししたものでしょうか」
「洋書だよ。このくらいの分厚さで、だいぶ重い。表紙が薄緑色の綺麗な本さ。おかしいなぁ」
「最後に見たのはどこでしょう」
「ええと、確かマクシムのやつの部屋だね。執務室で『裁可、不裁可、裁可、不裁可』って言ってる横で、長椅子に寝そべって読んだのが最後だ」
「『白龍には』」
「それが、さっきから姿が見えなくて。訊こうにも訊けなくて困ってる」
「老蕭館に用事があると仰せでしたので、では、すでにお発ちになったかもしれません。本は『白龍』がお持ちになったと考えてよろしいのでは?」
「だけど、消えたのは宝石についての解説書だよ。 老蕭館にわざわざ持っていくとも思えない。それに、毒物図鑑やら奇書の類ならわかるけど、あいつが俺の読むものに興味を示したためしなんか、いままでになかったけどなぁ」
* * * *
色街、花路である。
「どうした、飛」
界隈端の古妓楼二階。羅漢に低く問いかけられた。
狭い寝台で飛は起き上がるところ。短い声がもれたのをどうやら聞きつけられたらしい。
「大丈夫だ、羅漢。寝台を借りてすまなかった」
「なんの。寝床くらいいつでも貸すぞ。眠りが足りないと言っていたが、南荘はやはり帰るには不便か。いっそ東州茶房に戻ったらどうだ」
このところ急に冷え込みが増した。
夜を昼にして賑わう花路を守る仲間たちも、明け方には背を屈め、しきりに肩をさすっている。
白龍屋敷奥の南荘は、花路の束ね役のねぐらとしてはいかにも不便。
疲れて冷えた体を休めるには近い住まいを求めるべきだと、羅漢は日ごろから南荘に暮らすことには不賛成を唱えている。
暮らしぶりまで心配させているかと、飛はいささか苦笑顔になる。
「いや、格別不便とも感じていない」
「ならば、どうした。不眠に理由があるなら俺が相談に乗ろう」
「大したことじゃない。ただ、少々慣れないだけで」
「何だ? またあの『白龍』が何か」
そこにバタバタと忙しない足音が上がってきた。
「頭っ! 頭はいますかっ?」
バタバタバタンと飛び込んできたのは孫である。
「何だ、孫。もう少し静かに上がってこい。いま飛の悩みをだな……」
「これをどうぞっ、頭っ!」
叱る羅漢を押しのけ、孫が勢い込んで何かを差し出した。
見れば陶枕である。
枕だ。
「南荘の枕が合わなくて首の筋を傷め気味だと聞いたんで、ひとっ走りして探してきましたよ。 ほら、こいつはこうして炭をなかに入れて、あったかくできるんです。炭が熱けりゃ湯を入れてもいいそうです。 龍江街の奥方連中が愛用してるって話で。これなら冷える晩でも具合がいいでしょう?」
ぐい、と押し付けられて、飛はとりあえずありがたく受け取った。
「すまない、孫。だが、枕が冷たいのはかえって寝つくのにちょうどいい。 問題は高さだ。 白龍屋敷の侍女が気を利かせて上等を備えてくれたそうだが、どうも体に合わない。 この枕は、せっかく探してくれたものだ。冬場にありがたく使わせてもらおう」
「何だ、枕だと?」
悩みの理由を聞いた羅漢は、肩透かしをくらったような顔つきだ。
「俺はまた、あの『白龍』が夜な夜なおまえの安眠を妨げているんじゃないかと心配をだな」
「ああ。確かにそれも困りごとのひとつだが」
* * * *
白龍屋敷奥の南荘へ、侍女が届け物をしている。
主に言いつけられての使いである。
「それにしても『白龍』さまというおかたは、恐ろしく美しくて、おまけに恐ろしく変わっておいでだわ。寝台から新しい枕をのけて代わりに書物を置け、だなんて。 それにしても綺麗な本だこと。蕩けるような緑色。何という色かしら。 あら、これは……」
手にした届け物についつい見とれていて、はっと気づく。
ひと抱えもある分厚い本のあいだに、す、と一筋の銀糸が挟まっていた。
銀髪銀眸。
異相の主人の髪なのだわと悟って「まあ、どうしましょう」と戸惑った。
「下手に触ってあとからお叱りを受けても困るわ。このままで届けるのが、きっといいわ」
それでも興味を惹かれて、そっと本をひらいてみた。
そこに髪が落ちたということは、麗しい西里主人がその頁をひらいて見たに違いないと思うから。
異国の文字が並んで、書かれていることはまるでわからない。
けれど図版を眺めて楽しむことはできる。
「あら、この石は翡翠ね。そうだわ、この書物の表紙は翡翠色だわ」
夢見るように美しい色なのだわ。

illustrated by 浅見 侑さま(禁複製転載)
[白龍過眼]













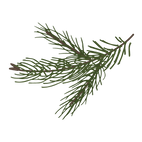
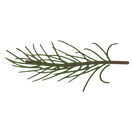

コメント