『飛花 龍唇を惑わす』
- yz0824
- 2023年3月31日
- 読了時間: 13分

誰かが言った。
〃物欲しげに揺れた花の罪に違いない〃
※ ※ ※
四龍島、白龍市の夜。
「なあ、マクシム。本当にいいのかい?
あとから万里にむっつり顔で小言を言われたりしないかい?」
葡萄酒の瓶を抱えたクレイ・ハーパーが、覚束ない足どりで暗い石段を降りている。
山の手の白龍屋敷から色街へと抜ける細道である。
ふだんこの道を通うのは、危急のときでなければ、色街を守る猛者ばかりだ。
ところどころに常夜灯がともされてはいるが、闇に慣れない目には
ありがたく映るほどではない。
「わわ……たどり着くまでに、瓶を落っことしそうだよ」
たびたびよろける友をふり返りもせずに、少々先を行くマクシミリアンが
みじかい嗤い声を吐く。
「よろしくなければ、あとから追っ手がかかるだろう。いまのところ屋敷執事どのの小言は聞こえてこない。
屋敷の門番は文句ひとつよこさずに通した。慌てて角灯を提げてついてきた取り次ぎ役も、戻れと咎める気配はない」
行く手に凶悪な賊が待ち受けるというならいざ知らず、おのれの街を歩むのに何の遠慮がいるものかと、石段の尽きるところに優雅に立った。
妓楼酒楼が並ぶ界隈の明るさのなかに、凄艶な美貌があらわとなる。
『白龍』マクシミリアン。
銀糸の髪、銀灰の瞳。異邦の血を色濃く宿す顔に、に、と笑みを浮かべ、
「いや、待ち受けているか。百余名の〃賊ども〃が」
愉しみだぞと声音に喜悦を滲ませる。
クレイ・ハーパーが最後の石段からとんで降りつつ、呆れる。
「だいたいね、マクシム。一介の門番やら取り次ぎ役やらが、ご主人さまに向かって意見できると思うかい?
あの万里だって、不賛成のときにはむっつり黙るか、さもなけりゃあ皮肉がせいぜいじゃないか。俺だって、こうして不平をつぶやくのが精一杯の抵抗さ。
厄介極まりない西里の『龍』に面と向かって文句を吐こうっていう物好きは、彼くらいなもんだよ」
「だからこうして殊勝にも足を運んでいる」
「と言っても、まさかわざわざ文句を言われに来たわけじゃあないだろう?」
「さあ、どうか。文句を吐くのが物好きなら、聞こうというこちらも物好きの極みだ。世辞や追従より、色街の頭の啖呵のほうがよほど耳に心地いい」
叱られてやろうというわけだと言って、色街のうちでももっとも賑わう大牌楼まえの道筋へと足を踏み入れた。
案内を請えと命じられ、青い顔の取り次ぎ役が楼のうちへととび込んでいく。
「ようこそいらっしゃいませ……なんですって!? 『白龍』さまが!」
慌てふためく声と足音がしばし乱れて聞こえ、ややあって楼の主人が息せき切ってあらわれた。
「ようこそお運びくださいました、梅雪楼へ。
あまりに急なこととて、十分なおもてなしができますかどうか。
はなはだ不安ではございますが、ささ、何はともあれ二階のほうへ」
如才ない主人の指図で艶やかな美女らが、わっ、とこちらを取り囲み、たちまち仙郷もかくやと言わんばかりの歓待ぶりとなる。
嬉々として酒瓶を持ち上げるクレイ・ハーパーが、
「グラスはあるかな? 本土からの船で葡萄酒が届いてね。むかしを思い出しながら飲もうと思うんだ」
四龍島に暮らすはめになって、まだ当分は海の向こうへ帰れそうもない。
せめて懐かしい酒を味わいながら友への恨み言を重ねるつもりなんだよと、あてこすりを言われて、マクシミリアンが平然と運ばれてきた杯を持ち上げる。
妓女が慣れない手つきで葡萄酒の瓶を傾けてよこす。
「本土のほうには、どのような遊びがございますの? 『白龍』さま」
なみなみと注がれる暗紅色に目をほそめつつ、マクシミリアンは応じる。
「この島とさして変わりはしない。酒、女、賭け事……そらぞらしい宴、騒々しい音楽に、危うい毒」
「まあ、毒!」
怖い、と驚く妓女のほうへは目もくれずに酒を飲み干して、
「毒と言えば、退屈ほど効き目の強い毒はない」
麗しい主の言葉を宴席での軽口ととったのだろう、女は和やかな笑い声をこぼす。
「あら。では、ご安心を。色街花路にその毒はございませんわ」
ついで月琴を抱いた妓女がそばに侍る。
肉、魚、蒸し物、湯、果物。湯気を立てる料理が先を争うように運び込まれる。
「やあ、旨そうだ! 見ろよマクシミリアン、この皿数。白龍屋敷より豪華じゃないか」
「執事どのに、そう教えてやるといい」
円卓を埋め尽くさんばかりの食器に、酒器。
白磁もあれば青磁もあり。色絵もあれば銀もある。
部屋を見渡すと、珍珠と瑪瑙のあしらわれた衝立やら、水晶の置物やら。
青灰色の袍に漆黒の風よけを羽織るマクシミリアンは、虎の毛皮を敷いた長椅子にゆったりと腰を据える。
女たちの器用な手が次々と料理を皿に取り分けてよこし、調子よく杯を重ねたクレイ・ハーパーの呂律がしだいに怪しくなった。
「しかしマクシム、良かったなぁ。一時はどうなることかと思ったけど、こうして白龍の街が落ち着いて、しじゅう花路の頭がそばにいて。
望みが叶って、おまえも居留区に暮らしてたときから比べると、だいぶ幸せなんじゃないのかい?」
硝子の杯を明かりに透かしながら、クレイはしみじみと懐かしむ。
「島に来たころは正直、気が気じゃなかったんだ。おまえは親父さんの墓に日参しちゃあ浮かない顔で。
一日も早く本土に帰らないと、俺はおまえがどうかなるんじゃないかって心配してた」
「そういえば口を開いては、帰りたい、帰ろうと嘆いていたか」
「そうさ! なのに、おまえときたら俺の頼みにはてんで知らん顔だった。
だいたいおまえは、むかしっから俺には冷たい。もっとも冷たいのは何も俺にばかりじゃなくて、特にご婦人がたにはつれなかったっけ。
本土じゃあ、いったい何人の女性を泣かせたんだか。いまだに取り殺されてないのが不思議だ」
聞き耳を立てる娼妓らに囲まれ、マクシミリアンは優雅に自嘲の笑みを吐く。
「あいにく取り殺したいと思うほどには愛されなかったということだ」
「そうかなぁ。俺はずいぶん見た気がするけどなぁ。手に入れたとたん、ぷいっと玩具に飽きが来る恋人のせいで、さんざん目を泣き腫らした美女たちを」
真偽の知れない昔話に女たちが白い顔を見合わせて笑いさざめくところに、階下から慌ただしい気配が伝わった。
口もとから杯を遠ざけたマクシミリアンが、す、とまなざしの色を変える。
「『白龍』!」
涼やかなその呼び声が、衝立越しに聞こえるか聞こえないかの刹那、
「遅いぞ、花路」
ずい、と立ち入る無遠慮な客を確かめもせずに、冷ややかな美声を部屋のおもてに向けた。
あらわれたのは漆黒の袍を身に纏う男だ。
色街花路の束ね役、飛である。
しなやかな細身に、良家の子弟とも見紛う品良い姿。
年若く、何とも清々しい見た目でありながら、その実、百余名の猛者連中を頼もしく率いて夜の街にある。
「仲間が知らせにとんできた。暇を持て余した〃龍〃が、界隈一の妓楼の上等の部屋でとぐろを巻いていると」
どういうことだと、性質苛烈をもって他市にまで聞こえる主に向かい、少しも臆せずぴしゃりと文句をよこした。
威勢のいい叱咤に、マクシミリアンは冷笑で応じる。
「その尾に巻かれようと、さっそく駆けつけたか」
「馬鹿な」
「ならば、主が浮気心を起こすまえにと、慌てて女どもとのあいだに踏み込むか」
海月の和え物を飲み込み損ねてむせながらクレイ・ハーパーが友に代わって言い訳する。
「すまないね、花路の頭くん。マクシムがどうしても花路で飲みたいって言いだして聞かないもんだから」
居留区の葡萄酒をどうしても色街で飲みたいとマクシミリアンが駄々をこねたものだからと、半分すまなそうに、半分おもしろそうに首をすくめた。
まっすぐにこちらを見据える花路の頭が、楼主人に向かい求める。
「娼妓たちを下がらせてもらいたい」
すかさずマクシミリアンは制する。
「妬心か、花路。無粋だぞ」
「何を言う、『白龍』。街の主が民に添うべき女を横取りして遊びほうけることこそ、無粋の極みだろう」
「ならば女どもを下がらせるといい。代わりに色街の頭が無聊をかこつ主を慰めてくれる」
でなければ承知しないと言い聞かせると、相手が「仕方なし」と顔をしかめるようだ。
楼主人の指図で、裙子の裾を引きつつ女たちが席から去る。
月琴の音もやんで、あとに残されるのは、贅沢な料理と、酒と、しらじらしい空気ばかり。
せっかくの宴をだいなしにしてくれた咎人を、マクシミリアンは機嫌よく責めた。
「値千金の夜をよくも邪魔してくれた」
「花路一の妓楼の商いを邪魔したのは、あんたのほうだ」
「色街も妓楼も四龍島西の街のうち。おのれの持ち物を弄ぶについて誰に何の遠慮がいる」
「果たすべき務めを果たしてから吐くべき台詞だ。値千金の一夜とやらは、それだけの値打ちのある客にしか購えない」
「では、花路。わたしの値は幾らほどだ」
見損なえばあとから高くつくぞと脅したところが、相手が意外にも、ふ、と語気を和らげた。
「さあ、どれほどだろう」
かたわらには、同じく花路を束ねる兄貴格の大兄が控えている。
拳を握り、肩をそびやかして、こちらの悪戯に苦りきる顔色だ。
が、しかし、頭を守る構えこそふだんと変わりはしないものの、逞しい体からはいささか億劫げな匂いが発せられている。
察するに、向こうは向こうで酒盛りを楽しんでいたものらしい。
見れば、きりりといつもどおり引き結ばれていると見えた花路の頭の口もとにも、ほんのわずかな綻びの気配があった。
すでに酔いのまわったクレイ・ハーパーが呂律の怪しい口調で言いつける。
「ねえ聞いてくれよ、花路の頭くん。知ってのとおり、マクシムのやつは子供時分から悪戯が過ぎる質でね……
本土で泣かせたご婦人は数知れず。だいたい、こいつは見た目がこんなだろう? いちいち呼び寄せなくたって、女たちが群がるんだよ。
それをいいことに居留区のご婦人がたに誘われては、今日はあっちの夜会、こっちの夜会……」
無駄話をつぶやいていたが、やがてよろよろとクレイは立ち上がる。
仁王立ちの大兄の肩に「おっとっと」と言ってすがると、
「眠い。俺は先に帰らせてもらうよ、マクシミリアン。あとのお守りはよろしく頼んだよ、頭くん」
面倒を預けられた相手が、迷う間もなく「おう」と返事をした。
「承知した。羅漢、居候どのを屋敷まで送ってくれ」
心得たと引き受ける大兄が歩みだし、クレイに肩を貸しつつ部屋から姿を消す。
艶めかしいしつらえの部屋に、二人きり。
色街にあってよほど信頼され、頼みにされているのだろう。
楼の主人は、厄介な客の相手をすっかりまかせて、あれきり様子見にさえ引き返してこない。
凄艶な微笑を浮かべ、マクシミリアンは花路の頭を見やる。
「つき合え。わたしを心地よく酔わせるのは、おまえの役目だ」
長椅子を立って寝台へと席を移し、酒と杯を手に「来い」と相手に強いた。
応じて歩み寄る男の手首をとらえ、無理やりかたわらに引き寄せる。
しなやかで細いが、その体は力を秘めている。
なめらかに張り詰める肌の内側は、清冽な気迫と熱とで満ちている。
抗う気があれば、いかにこちらが強いたところで、きっぱり抗うことだろう。
だが今夜は唯々諾々とそばに寄る。
すでに飲んできた酒のせいか、それとも単なる気の緩みか。
「飲め。おまえが酔い潰れたなら、先ほどの娼妓どもを呼び戻す」
もしも色街に風紀というものがあるとして、それを乱されるのが嫌なら飲むことだと命じると、相手が、くすり、と苦笑した。
潔く差し出される杯の深みを、暗い色の酒で満たしてやる。
仲間と酌み交わしたのは青龍あたりの火酒か。
咲き崩れる寸前の花に似るあまやかな匂いが、吐息のうちにかすかに香る。
「あんたの〃子供時分〃とやらが偲ばれる」
皮肉のつもりだろうが、口ぶりには生来のやさしさが滲む。
いまいましい隙を見せるものだと嘲笑いつつ、マクシミリアンは立てつづけに酒を干し、相手にも杯を重ねさせる。
色街暮らしの証の衣装の肩に、艶やかな髪がさらりとこぼれている。
街と街とが相争う危難のさなかをくぐったというのに、頬、首筋、拳、明かりにさらされた素肌のどこにも傷らしい傷はない。
日ごろは容赦なくこちらを睨むまなざしが、いまは色香を漂わせ、酔っている。
七杯、八杯と来たところで、
「『白龍』。俺は、このあたりでもう……」
やめておこう、と断りかけた相手にマクシミリアンは、に、と冷たい笑みを突きつけた。
「酔ったか」
「いや」
「酔ったろう、情けなく」
「なん、の」
「では飲め」
「おう」
「さらに飲め」
さらに杯を干せと強いるうち、ついに相手がゆらりと体を傾けた。
抗いがたい酩酊に襲われるのだろう、顔をしかめてまぶたを閉じる。
寝台に手をつこうとする花路の頭を、やおら抱き留め、褥の上へと横たえた。
淡い輝きを放つ絹の波に、力なくその四肢が投げだされる。
「酔い痴れたな、不覚にも。このわたしの目のまえで」
否と応じるかわりに胸を開いて喘ごうとする相手を、ぐ、とそのまま組み敷き、身動きを封じて、
「なあ、花路」
そばにいればいいというわけではないぞ、と。
脅して聞かせるが、いらえはない。
酔っている場合かと重ねて難じつつ、その顔を間近に見下ろした。
「心惹かれる質だろう、凶事というものに……」
おまえが酔い痴れるわけを、知っている。
ありきたりの安穏に親しもうとして、けれど、できないからだ。
平穏無事を喜ぶふりをしながら、実は狂気を求めるからだ。
穏やかな眠りのなかにいつか首をもたげるであろう悪夢を待ち望み、いっそ食い破られたいと願う。
はしたない欲に気づかれまいと、おのれでおのれを偽るからだ。
揺れる翡翠に飾られた耳朶に「寝ている場合か」と低く囁いた。
首を振って逃れようとするのを、顎をつかんで引き留める。
喉を圧す指にじわりと力を加えて、堪らず身をよじる様を冷ややかに見た。
「耐え難い災厄とは本来、おのれを内側から苛むものだ。おまえはまだ、戸外に吹き荒れる嵐しか知らないだろう」
長く誰かに守られ、幸いにもそれを知らずにきたに違いない。
あまりに清廉。
あまりに真摯。
みずからのうちに生ずる凄まじい災いというものを、いまだ味わわずにいる。
「ならば、これから思い知るといい」
ゆっくりと覆い被さりつつ眺める相手は、猛者どもを従えるとは思えないほど清らかだ。
出会ったばかりのころの激しさは、いつの間にか穏やかに失せている。
敵意に煌めき、不審に翳り、時に恋情とまがうばかりの熱を押しつけてよこした瞳も、閉じたまぶたに隠されていまは見えない。
過ぎた口説きを恥ずかしげもなく吐いたくちびるが、安らかな吐息をもらし、薄い笑みさえ浮かべている。
酒に濡れたそこに、
「っ……う」
不意の痛みに呻いた相手が、しかし目覚めないまま深く、底知れない眠りに堕ちた。
やおらマクシミリアンは身を起こす。
寝入る男を冴えたまなざしで一度だけ見やり、すいと寝台から立ち降りる。
部屋をあとにして階下へくだると、慌てた楼の主人が駆けてきた。
「『白龍』さま? 我らが頭は?」
「〃我らが頭〃はどうやら酒に飲まれたとみえる。大兄が迎えに戻るまで眠らせておくといい」
「頭が? まさか、あなたさまのお相手を申し上げずに、お休みに?」
「ああ。性悪な『龍』の機嫌を取ることも忘れて夢のなかだ。よほど西里という街は安泰らしい」
祝着至極。
何よりだと、冷たく嗤って歩みだす。
「お、お待ちください。せめてお屋敷までお供を……でないと、あとからわたくしどもが頭に叱られます」
「必要ない。深酒を好む夜の街の男どもより、よほど闇には親しんでいる」
慌ただしく店のものに案内の指図する主人を尻目に、賑わう道に出る。
『白龍』だ、『白龍』さまだ、と四方からかしましい声がよこされる。
夜風に無数の花燈籠が揺れている。
暗紅色の酒の渋みが、舌先と、くちびるの端とを汚している。
「毒、か」
……毒だぞ。花路。
illustrated by 浅見 侑 さま[禁複製転載]













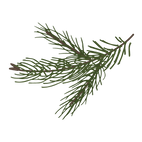
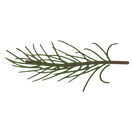

コメント